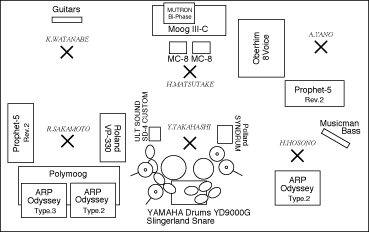TRANS ATRANTIC TOUR '79
|
通称「第1次ワールド・ツアー」と呼ばれるライブは、1979年秋
に行われ、ロンドンを皮切りに、パリ、ニューヨーク、ワシントン、
ボストンなど5都市7公演を行った。
この前哨戦とされるのが、1979年8月のLA・グリークシアター・
ライブ。デビュー直後のYMOに注目していた米国ニューウエーブ・バ
ンド「チューブス」のオープニング・アクトとして演奏した。
YMOは当初、音楽的に保守的な米国よりは、パンクなどが全盛であっ
た欧州の方が受け入れられるだろう、との見方が強く、ツアーも欧
州優先のスケジュールが組まれていた。
しかしながら『どうせ、わかんねえよ。こういうの』というアメ
リカでのライブは前座としては異例のアンコールを受けるほど盛り
上がった。この急遽行われた米国での成功で、一気に世界に飛び出
すことになる。
まだアルバムを1枚しか発表してない"正体不明のジャパニーズ・
バンド"に対する海外マスメディの高い評価、YMOで踊るファッショ
ナブルなオーディエンスの映像が逆輸入され、帰国後に「来日した
初の日本人アーティスト」としてYMO人気は爆発する。
|
ステージ・セッティング
|
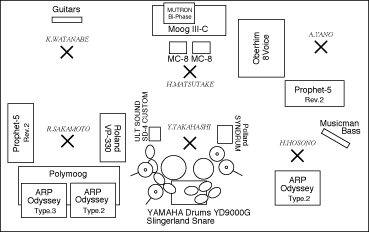
|
厳密には1次ツアーには含まれないが、YMO初の海外公演のLA・グ
リークシアターでのセッティング。基本的に同じセッティングでツ
アーが行なわれる。機材は、ほとんどがプログラマーである松武秀
樹所有のもので、1st/2ndアルバムでも多用されていたMoog III-Cと
ARP Odysseyがメイン・シンセ。坂本教授は「メロディーはPolymoog/
ソロはARP」と使い分けていたようだ。
その他、YMOのライブ・サウンドの秘訣ともいえる、アナログ・ディ
レイのヤマハE-1010、効果的にSEに使ったMUTRON Bi-Phase、クリッ
ク用のBOSS DR-55などは松武ブースにセッティングわれていた。今
見ると可笑しいが、Moog III-Cにはクリスマス・ツリーのような電
飾が付けられ「より機械チック」な視覚的演出として、その得体の
知れない機械が発する音にワクワクしたものだ。
『(飛行機も)まだファースト・クラスじゃなかった』という1
次ツアーは、会場こそライブ・ハウス規模であったが、赤い人民服
というファッションはもちろん、ステージ上の膨大な機材、コンピュ
ーター・プログラマーの存在、科学の実験を行っているかのような
パフォーマンス、カウントなしでいきなり始まる演奏、ヘッドホン
を付けてアンドロイドのように無表情な演奏風景は各地で驚異的に
受けとめられた。
|
ONE MORE YMO!
TRANS ATRANTIC TOUR '79曲目解説
|
M-3:BEHIND THE MASK
M-4:COSMIC SURFIN
LA・グリークシアター@1979.8.4
|
YMOが海外で演奏した最初の曲が「BEHIND THE MASK」。キックか
ら始まる「ドダダダ、ドダダダ」というドラムのフィル・インが印
象的。「東風」や「千のナイフ」といったクラシック的な作曲が多
かった坂本教授が『(この曲で)一気に変わった』というYMOの代
表作。
『景気がいいんだよね、元気な演奏で』という「COSMIC SURFIN」
は、8ビートが生き生きした演奏で、とてもリラックスした演奏。
『シーケンサを使わなくてもやれたという、YMOの代表的な演奏スタ
イル』で、『終った後に楽屋で大はしゃぎした』というほど成功し
たライブだった。
|
M-9:TONG POO
M-10:THOUSAND KNIVES
M-17:TECHNOPOLIS
ロンドン・ヴェニュー@1979.10.16,24
|
「TONG POO(東風)」は、『アカデミックさと、その静かさ』を
持つ坂本独特のメロディーを持つ楽曲だが、『演奏はわりとドライ
ブして』おり、その『微妙なマッチング』が大いにウケた。コード
がどんどん変わる曲で、難易度も高い。
一方で、坂本教授のソロ作品としての色が強い「THOUSAND KNIVES」
は、一種『現代音楽的なアカデミックな要素』に対して、高橋のド
ラミング(特にハイハット・ワーク)も圧巻だ。『R&Bの8ビートに、
みんなが16ビートで乗ってくる』というドライブ感覚が見事な演奏
で、両曲とも渡辺香津美のギター・ソロも聴きごたえがある。
「TECHNOPOLIS」は、『YMOの代表曲でありながら、海外ではあま
りやってません。難しいんです(笑)』と、オリジナルが音色の変
化が多彩で、またボコーダーを使うなど、シンセ担当が忙しい。さ
らに『ベロシティ(コントロール)がまだなくてね。ボリュームは
教授が足のペダルとかで調整していた』と、演奏に苦心していたよ
うだ。
ツアー初日のロンドン・ヴェニューでは、満員で会場に入れなかっ
た観客のために急遽アンコール公演が行われる。一気に世界中のミュ
ージシャンにその存在を知らしめる一方で、パンク/ニューウェーブ
と世界のミュージック・シーンの最先端を行っていたロンドンでは
『客の方がステージの僕たちよりもカッコいい(笑)』というほどフ
ァッショナブルで、華やかなライブでもあった。
|
M-5:DAYTRIPPER
M-7:LA FEMME CHINOISE
M-8:CASTALIA
NY・ボトムライン@1979.11.6
|
シンセ・ベースの「ダダダン」から始まる「DAYTRIPPER」はお馴
染みビートルズの曲。『裏から入って、変拍子とか入れて、どこが
頭なのかわからない始まり方』をするアレンジは、なんとムッシュ
こと、かまやつひろしのスパイダースが演奏していたものがヒント
だった。この『裏ビートから入るカタチ』は、後の高橋の作品に数
多く見られる。
「LA FEMME CHINOISE」は、代表的なボーカル・ナンバーで、ライ
ブの度にさまざまなアレンジで演奏しているが、ここでは『個人的
にも好きだった』というオリジナルに忠実なバージョンが選ばれた。
やはり最大の聴きどころは、ユキヒロ(あえてカタカナ)のボーカ
ルで、出だしの歌詞から『フーマンチュー唱法』と呼ばれ、YMO/ユ
キヒロ・ボーカルのオリジナリティーを確立した曲である。また、
シーケンサを使わないこの曲には『独特のスピード感』があり、特
にボトムラインでの演奏は秀逸だ。
「CASTALIA」は、1次ツアーのオープニング曲。この後にボコー
ダーによる「We are YMO. We are from TOKIO, JAPAN.」という挨拶
の後にライディーンが始まるという『重要な導入曲』であった。
少々話しは逸れるが、ボトムラインの演奏は、当時FM放送でオン・
エアーされているので聴いたことのある読者も多いと思うが、その
PAのミキシングはひどかった。矢野顕子のバッキングが、坂本教授
のメロディーの10倍くらいの音量なのだ。これは、単にミキシング
のミスだけなのではなく、当時プロのPAでさえも始めて聴くシンセ・
バンドをどう対処してよいのかわからなかった結果であろう。それ
ほど未知の音楽であり、衝撃として受けとめられていた(今回のCD
では、高橋の手によりマスターからミキシングしなおされているの
で、そのような心配はない)。
|