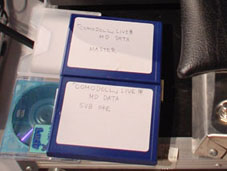●Fender Japan JAZZ MASTER, Marshall JCM2000
ハヤシの2本のギターは、どちらもFender Japan JAZZ MASTER。
このうち、画像右側のエメラルド・グリーンのボディーのギターは、ネ
ックがゾディアックのものに交換されている。ベンチャーズも使ってい
たというJAZZ MASTERだが「ニュウエーブ・ギターは、やっぱりシン
グル・ピックアップ!」というこだわりがギターにもにじみ出ている。
アンプはMarshall JCM2000。一般的にJAZZ MASTERとMarshall
は相性が良くないと言われるが、JCM2000のディープなサンドとはマッ
チしている。
「DEVOとかP-MODELとかすごい好きだけど、何がカッコよかったかっていうと、やっぱりあのルックスとサウンドで
すね。P-MODELも、学生みたいな人達が目ひんむいてジャンプしてパンク歌ってるとか。それと、もっと単純にシンセ
の音とか、ギターの変態的なリフとか、リズムボックスの音とか、奇抜なシンセ音とか。リズムボックスやボコーダー
の音は今でも大好きですね。そこだったんですよね。だから、社会風刺とか何かを訴えるということは、僕にとっては
どうでもよくて、単純に音とか、雰囲気とか、そっちの方が重要でした。
でもギターの音は、いまいち納得いかなくて。僕はジャキーンって鳴ってる方が好きで、ペナペナしたギターをノン・
エフェクトで鳴らすとか、そういった音は好きじゃなくて。それにコーラスとフェイザーでチャカチャカした音もダメな
んですよ。歪むのか、歪ませないのかハッキリしろよ!っていう(笑)。DEVOは、そんなギターがさらにツインですか
らね(笑)。そこらへんは自分ならこう鳴らす、という感じでポリシックスのサウンドは作ってます。(ハヤシ)」

そんなハヤシのエフェクターは、BOSSのDS-2(TURBO DISTORTION)だけ。
2種類のターボ・モードで、オーソドックスなディストーション・サウンドから、
フル・ボリュームでアンプを鳴らしたような、超ヘビー級の歪みが得られて、その
サウンドMarshallアンプともよくマッチする。ライブでは、まさに「これ一発の
み!」なのである。
 カヨ/シンセサイザー、ヴォコーダー、ボイス
カヨ/シンセサイザー、ヴォコーダー、ボイス

●KORG Polysix&Clavia DMI Nordlead2
下段は、バンド名の由来でもある、KORGのPolysix。1981年に発売
された6音ポリフォニックのアナログ・シンセサイザーで、32種類の音
色メモリーに、コーラス、フェイザーなどのエフェクトも搭載されてい
る。このシンセは、中古屋めぐりをしていたハヤシが、ルックスと音の
良さに惹かれて即購入したという。結局、バンド名にするほどの大のお
気に入りシンセだ。
上段の、赤のボディーでお馴染みのクラビアDMIのNord lead2は、カ
ヨの所有キーボード。DSP技術を使ってアナログ・シンセをシミュレー
ションするデジタル・シンセサイザーで、『SPARK』などでメインに弾
かれていた。
ちなみに、アンコールの『ENO』では、ハヤシが写真の向こう側(つまりリア・パネル側)から、頭を突っ込んで
PolysixとNordlead2を弾いていた。

●BIAS BS-2
『each life each end』で、カヨがチョップして「ピュ〜ン!」と鳴
らしていたのが、イシバシ楽器のオリジナル・ブランドであるBIASの
BS-2の復刻モデル。以前のライブではスガイのスネアにもセッティング
されていたが、今回のツアーではドラムには使われていないようだ。
オリジナル・モデルは、まずBS-1として1980年に発売。本体そのも
のが振動ピックアップの構造となっており、スネアのリムに取付けるだ
けで簡単にシンセ・ドラム・サウンドを鳴らせた。世界で最も小さく最
も安いシンセとして売り出されたが、当時YMOのドラマーであった高橋
幸宏がワールド・ツアーに使用して、一躍テクノ・キッズの人気アイテ
ムとなった。その高橋幸宏の「ホワイト・ノイズを組み込めないか」と
いうリクエストに応えて発売されたのが、このBS-2。
VCOをSWEEPさせて、それに変調をけかるだけの簡単な仕組みだが、変調のRATEとMODEの組合せで、いろんな面白
い音が作れる。復刻版は、オリジナルよりも若干サイズが大きくなって、ボディーの素材がダイキャストから樹脂に変更
され、また電源アダプター・ジャックが無くなり、電池取り出し用の蓋が新しく追加されたデザイン。とってもチープで、
アナログらしいパーカッション・シンセだ。

●Novation BassStation&Digitech TALKER
ポリシックス・サウンドの中心でもあるボコーダー(いわゆる、ロボ
ット・ボイス)は、Novationの小型アナログ・シンセサイザーBass
Stationと、DigitechのエフェクターであるTALKERの組合せ。つまり、
クラフト・ワークやYMOでお馴染みの単体のボコーダー・シンセサイザー
を使っているのではなく、エフェクターを使った「ボコーダーみたいな
ロボット・ボイス」を作り出しているのだ。
BassStationは、もともとハヤシが1台を所有していたが「壊れた時用に」と、ネット・オークションで2台目をゲッ
トし、そちらは現在ではレコーディング用として使っているとのこと。このオークションには逸話があって、出品者の商
品説明に「DEVOやポリシックス好きには最適!」と書かれていたという(笑)。さらに、落札後にハヤシが連絡を取っ
たところ、なんと相手は専門学校時代のハヤシの同級生だったというから驚きだ。ライブ用のBassStationは、ツアー後
半で少々調子がよくなかったようだが、ツアー・ファイナル前には治療が施され、当日は万全の状態であった。
「ボコーダーは、BassStationとTALKERの組合せです。これは僕の中では一番のボコーダーです。KORG MS2000とか
いろんなボコーダーを試したんですが、どうもショワショワ〜っていう腰の弱さがポリシックスに合わないんですよね。
ポリシックスというか僕に合わない。やっぱりあのガチっとした、クラフトワークみたいなバリバリのロボット・ボイス
が好きなんです。薄っぺらくてナヨナヨしたのがダメなんです。そういう好みで、今のところイメージした音が出せるの
はこの組合せだけなんですよ。ここまでやってる人はいないと思います。BassStationは、和音は出せないんですが、
VCOを2つ鳴らして、そのひとつのピッチをズラして和音的に使ってます。
アルバム5曲目の『COMMODOLL』にしても、普通のショワショワした弱いボコーダーで歌うと、曲の最後までもたな
いんですよ。だから、『COMMODOLL』は、この組合せで成り立った曲んだな、と思います。(ハヤシ)」

TALKERというのは、もともと人間の声にモジュレーションをかけて
ロボット的な音色に変えるもので、さらに入力したギターやシンセなど
の楽器音と混ぜ合わせて、音階を付けて演奏できる、ユニークなエフェ
クターだ。

●TASCAM MD-301mkII,YAMAHA MD4&Digitech TALKER
ポリシックスのシーケンス・フレーズは、MDを使って演奏されており
そのコントロールはカヨが行っている。ラックに入っているのが、TAS-
CAMのMDプレイヤーMD-301mkII。ラック上には、バックアップ・ディ
スクが見える。アンコールの『ENO』では、ハヤシ自らがこのプレイヤー
の再生ボタンを押して、宇宙人パフォーマンスが始まった。
ラック上に置かれたYAMAHA MD4と右手のDigitech TALKERは、ハヤシのボコーダー・ボーカル用のセットで、
『COMMODOLL』と『BECAUSE』で使われた。TALKERには、ハヤシのボコーダー用マイクとMD4が接続されており、
MD4からはあらかじめボーカル・メロディーが収録された演奏がTALKERに送られる。この方法により、ギターを弾き
ながら歌うハヤシのボコーダー・ボーカルにも、ビブラートなどのコントロールが可能となっていたわけだ。
 フミ/ベース
フミ/ベース

●YAMAHA SBV
フミが使っていた2本のベースは、共に20フレット/2ボリューム/
1トーンのパッシブ仕様のYAMAHAのSBVだが、どちらもピック・ガー
ドは特注となっている。特に写真左のレッド・ボディーのベースは、ネッ
ク裏を塗装したり、ヘッドのYAMAHAマークを金具に改造するなどの特
注品だ。
市販品のSBVには、ジャズベース用ピックアップがフロントとリアに2
つついており、ベンチャーズやGSブーム時に流行ったスタイルのベースで、
いわゆるテケテケ・サウンドの代表選手と言える。このうちフロント・ピ
ックアップをプレシジョン・タイプに交換することで、低音がきれいに取
れるようになることが特長だ。

●AMPEG SVT II+SVT-810
ベース・アンプは、AMPEGのSVT II+SVT-810(アンプ・ヘッド+キ
ャビネット)の組合せ。プリ/パワー部共に真空管を使用したヘッドで、
ストレートで非常にオトコらしい(!)音のするベース・アンプの定番。
これでポリシックス・サウンドの土台をガッチリと作っている。ヘッド・
アンプの真空管の様子は、ライブ・レポートのトップ・ページのアニメー
ション画像でチェックして欲しい。キャビネットは10インチ×8発、総重
量75kgという、これまた男らしいサウンドを発する代表選手だ。

●LINE6 POD,Tech21 SANSAMP CLASSIC
エフェクターには、ギター用のアンプ・シミュレーターとして人気の
LINE6 PODを使用。『COMMODOLL』の冒頭と、『SPARK』の曲中で
ファズとして使用していた。一方、Tech21のSANSAMP CLASSICも
定番のチューブ・アンプリファイアー・エミュレーターで、8つのミ
ニ・スイッチによりマーシャルやブギーなどのアンプをシミュレート
できる。ディストーション・サウンドだけでなくクリーンなサウンド
も作りだせる。この他に、フットスイッチのセレクターやチューナー
にはBOSSのコンパクトが使われていた。
 スガイ/ドラム
スガイ/ドラム

●CANOPUS Drums Set
知る人ぞ知る、CANOPUSのドラム・セット。ブルーのメタリック・ボディーの
キック、タム、フロア・タムとスネアという、いたってベーシックなセット。あの
力強いスガイのドラムは、たったこれだけのシンプルなドラムから生まれる。
「実は、私もポリシックスはインディーズ時代から聴いてまして、スガイさんが店に来た時は“あっ!ポリシックスだ!”
って思いましたよ(笑)。スガイさんもドラムを選ぶ時に“僕らはラウドなロック・バンドだから”という事をよく言っ
てました。実際、CANOPUSのドラムは音がデカイんですが、AXのライブでもしっかりと鳴ってくれていたし、ギターや
ベースとのバランスもよかったので安心しました。(CANOPUS 久保泰晴氏)」
また、残念ながら写真には収められなかったが、スガイのパワフルなドラムを支えるもう一つの重要なアイテムとして、
小型扇風機がスガイの背後に控えていた(笑)。
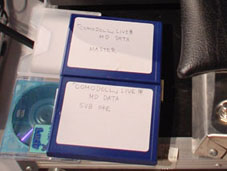
●文&撮影:布施雄一郎

POLYSICS WORLD TOUR 2001 FINAL Top Page
POLYSICS OFFICIAL SITE
Top Page
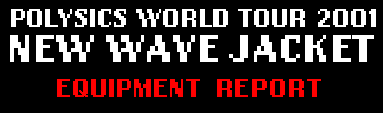
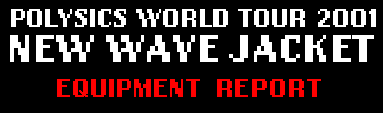

ハヤシ/ギター、ボイス、プログラミング


カヨ/シンセサイザー、ヴォコーダー、ボイス





フミ/ベース



スガイ/ドラム